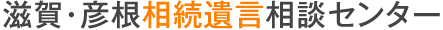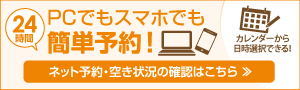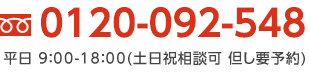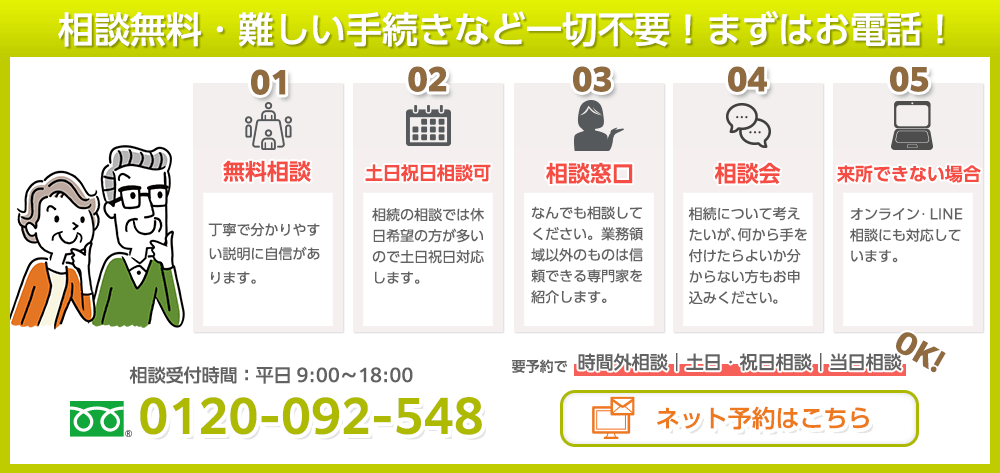自宅は妻に、現金は子に。「おしどり贈与」と「配偶者居住権」、どちらがトク?メリット・デメリットと登記の重要性
自宅は妻に、現金は子に。「おしどり贈与」と「配偶者居住権」、どちらがトク?メリット・デメリットと登記の重要性
こんにちは。「司法書士法人 おうみアット法務事務所」です。
「私が先に亡くなっても、妻がこの家に安心して住み続けられるようにしたい。でも、財産は自宅がほとんどで、子どもたちに現金をあまり残してやれないかもしれない…」
長年連れ添ったご夫婦にとって、これは非常に切実な悩みです。
ご主人が亡くなった後、奥様が住む場所を確保しつつ、お子さんたちへの相続も円満に進める。この課題を解決する方法として、最近よく耳にするのが**「おしどり贈与」と「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」**です。
どちらも「配偶者が自宅に住み続けられるようにする」ための制度ですが、その仕組みやタイミング、税金、そして**「登記(とうき)」**の必要性は全く異なります。
今回は、60代以上のご夫婦や、次の相続(二次相続)まで見据えている方に向けて、登記の専門家である司法書士の視点から、この2つの制度を徹底比較します。
1.「おしどり贈与」とは?(生前に自宅を贈与する)
「おしどり贈与」とは通称で、正式には「贈与税の配偶者控除」という税金の特例制度です。
- いつ使う?: 生前(夫が元気なうち)
- どんな制度?: 婚姻期間が20年以上のご夫婦間で、居住用の不動産(またはそれを取得するためのお金)を贈与する場合、最大2,000万円まで贈与税がかからないという制度です。(基礎控除110万円も別で使えます)
- 権利はどうなる?: 自宅の「所有権」そのものが、夫から妻へ移ります。
💡 司法書士からの最重要ポイント:『登記』が必須です!
この制度で一番大切なことは、「贈与しました」という口約束や契約書だけでは法的に完了しないということです。
税務署に「おしどり贈与」の申告をするためにも、そして法的に「この家は妻のものだ」と確定させるためにも、必ず「所有権移転登記(名義変更)」を法務局に申請しなければなりません。
登記をしないままご主人が亡くなってしまうと、「贈与は成立していない」とみなされ、結局その自宅は相続財産として扱われてしまい、相続人全員での遺産分割協議が必要になる…といったトラブルにもなりかねません。
2.「配偶者居住権」とは?(相続時に「住む権利」を遺す)
こちらは、2020年4月の民法(相続法)改正で新しく作られた権利です。
- いつ使う?: 相続時(夫が亡くなった後)
- どんな制度?: 奥様が亡くなるまで(または一定期間)、その自宅に無償で住み続けられる「権利」を相続する制度です。
- 権利はどうなる?: 自宅の権利を「住む権利(=配偶者居住権)」と「所有権(=負担付きの所有権)」に分けます。
【具体例】
遺言書で「自宅の配偶者居住権は妻に、所有権は長男に相続させる」と定めます。
- 妻(奥様): 所有者ではないが、亡くなるまで家賃なしで住み続けられる。
- 長男(お子さん): 所有者になるが、お母さんが住んでいる間は自分で使ったり、勝手に売ったりできない。
💡 配偶者居住権の最大のメリット
この制度の利点は、奥様が相続する財産の「評価額」を下げられることです。
例えば、3,000万円の自宅を奥様が「所有権」で相続すると、奥様の相続分は3,000万円と評価されます。
しかし、「配偶者居住権」で相続した場合、その価値が1,500万円(※年齢などで変動)と評価されれば、残りの1,500万円分、預貯金など他の財産を多く相続できるようになります。
3.徹底比較:「おしどり贈与」 vs 「配偶者居住権」
では、どちらがご自身の家庭にとって「トク」なのでしょうか?一覧表で比較してみましょう。
| 比較ポイント | 💖 おしどり贈与(生前贈与) | 🏡 配偶者居住権(相続) |
| タイミング | 生前 | 相続発生時 |
| 必要なもの | 贈与契約書(+婚姻20年以上) | 遺言書 または 遺産分割協議 |
| 得られる権利 | 所有権(完全な自分のもの) | 居住権(住む権利のみ) |
| 登記(名義変更) | 【必須】 しないと贈与が完了しない | 【推奨】 登記しないと第三者に対抗できない |
| メリット | ・妻が完全な所有者になれる ・妻は自由に売却や賃貸ができる | ・妻が預貯金なども多く相続できる ・二次相続(妻の相続)の節税になる |
| デメリット | ・登録免許税や不動産取得税が高い ・妻の「次の相続」では課税対象になる | ・妻は自由に売却や賃貸ができない ・固定資産税の負担は妻が負う |
| 固定資産税 | 妻(新しい所有者) | 妻(使用者が負担) |
4.結局、どちらを選ぶべき?(司法書士の視点)
どちらの制度にも一長一短があり、「どちらが絶対におトク」とは言えません。ご家族の状況や想いによって、選ぶべき道が変わります。
💖「おしどり贈与」が向いているケース
- 「妻にすべての決定権(売却など)を渡して、完全に安心させたい」
- 「自分の意思がハッキリしているうちに、生前に名義変更を済ませておきたい」
- 「自宅以外の財産(預貯金)も十分にある」
ご注意点: 生前贈与は、相続時に比べて登記費用(登録免許税)や不動産取得税が高額になる傾向があります。
🏡「配偶者居住権」が向いているケース
- 「妻の住む場所は確保しつつ、預貯金もできるだけ多く妻に残したい」
- 「自宅は最終的に長男に継がせたいが、妻が亡くなるまでは妻に使わせたい」
- 「(重要)二次相続まで考えて節税したい」
- →奥様が亡くなった時、「配偶者居住権」は消滅するだけなので、奥様の相続財産としてカウントされません。結果的に、お子さんたちの相続税負担を減らせる可能性があります。
ご注意点: この権利は「遺言書」で定めておくのが最も確実です。また、この権利を守るためには「配偶者居住権設定登記」をしておくことを強くお勧めします。
5.まとめ:手続きの実行には「登記」と「専門家」が不可欠です
「おしどり贈与」も「配偶者居住権」も、奥様が安心してご自宅に住み続けるための素晴らしい制度です。
しかし、どちらを選ぶにしても、
- おしどり贈与 → 贈与契約書の作成 と 所有権移転登記
- 配偶者居住権 → 公正証書遺言の作成 と 将来の 相続登記・居住権設定登記
といった、法的に複雑で重要な手続きが必ず発生します。
「自分たちの場合は、どちらが合っているんだろう?」
「実際に手続きを進めるには、何から始めればいい?」
こうしたお悩みをお持ちなら、ぜひ一度「司法書士法人 おうみアット法務事務所」の無料相談をご利用ください。
ご家族の想いを法的に実現するため、登記と相続の専門家として最適なプランをご提案します。