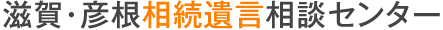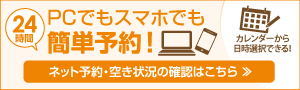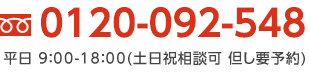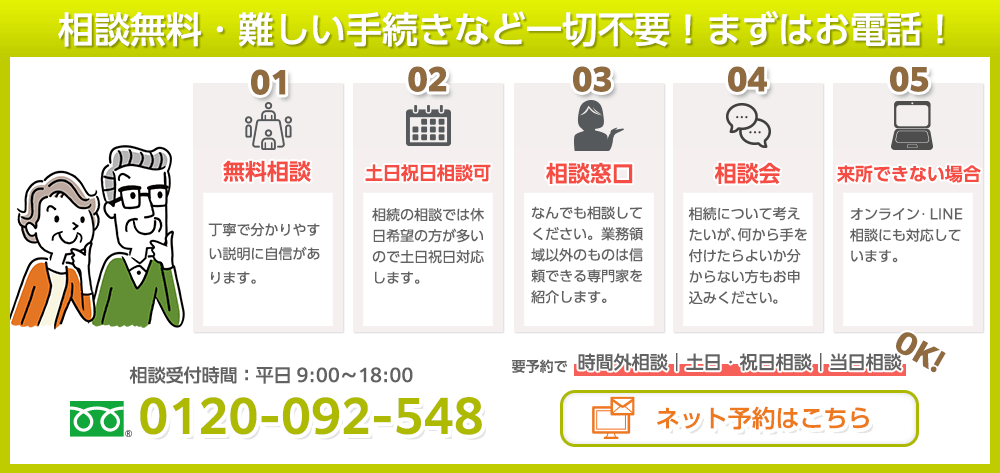二種類の「後見」の違いとは?~成年後見制度と任意後見制度~
目次
- 成年後見制度を利用する人は増加している?
- 後見には二種類ある!任意後見と法定後見の違い
- 任意後見制度を利用した実際の活用事例
- 成年後見人はどのような人が選ばれるのでしょうか?
- 成年後見人の役割は何ですか?
- 成年後見制度の費用はどのくらいかかるのでしょうか?
成年後見制度を利用する人は増加している?
近年、認知症や高齢化問題が深刻化する中で、成年後見制度を利用する人が増加しています。厚生労働省のデータによれば、成年後見制度の利用件数は年々増加し、令和元年末時点で約21万件に達しています。
しかし、利用者が増加する一方で、制度の硬直性や使い勝手の悪さが指摘されており、利用をためらうケースも少なくありません。また、近年注目されている家族信託など、柔軟な財産管理手段への関心の高まりも、成年後見制度の利用を制限している要因の一つと言えるでしょう。
後見には二種類ある!任意後見と法定後見の違い
成年後見制度には大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです:
法定後見
- 開始時期:本人の判断能力が低下した「後」に手続きを開始。
- 支援の種類:本人の判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があります。
- 後見:判断能力を「欠く」状態。最も強い支援が必要。
- 保佐:判断能力が「著しく不十分」な状態。中程度の支援が必要。
- 補助:判断能力が「不十分」な状態。軽度の支援が必要。
- 支援目的:本人の財産保護が主目的。家庭裁判所による管理が強く、本人の自由度は制限されます。
任意後見
- 開始時期:本人が元気なうちに契約を結び、判断能力が低下した「後」に契約が発動します。
- 支援の種類:契約内容に基づき、本人が希望する支援内容を自由に設定可能です。
- 支援目的:本人の意志を尊重し、柔軟に対応できる支援が可能です。
- 注意点:任意後見契約は本人の判断能力が低下する前に結ばなければならず、発動後は任意後見監督人が裁判所から選任されます。
法定後見が「行政処分による保護措置」であるのに対し、任意後見は「本人の自由意志に基づく契約」である点が最大の違いです。
任意後見制度を利用した実際の活用事例
70代後半のAさんは、一人暮らしで物忘れが気になり始めたため、将来の不安を解消する目的で任意後見制度を活用しました。以下の支援内容を契約しました:
- 任意後見契約:将来の認知症発症に備え、財産管理や身上監護の支援を契約。
- 財産管理契約:現在の財産(通帳や不動産)の管理を身近な家族に依頼。
- 見守り契約:定期的に訪問して健康状態や生活状況を確認。
任意後見契約は、柔軟な支援が可能であり、財産管理契約や見守り契約を組み合わせることで、将来の不安を軽減する仕組みを整えることができます。
成年後見人はどのような人が選ばれるのでしょうか?
法定後見の場合
- 家庭裁判所が成年後見人を選任します。
- 家族や親族が選ばれることもありますが、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるケースも少なくありません。
任意後見の場合
- 本人が信頼できる人を自由に選任できます。
- 家族や親族に加え、弁護士などの専門職に依頼することも可能です。
成年後見人の役割は何ですか?
- 身上監護:施設入居手続きや契約代行など、本人の生活に必要な法律行為を代理。
- 財産管理:本人の財産を管理し、不正や損失を防ぎます。
任意後見では、これらの役割を個別に設定可能で、柔軟な対応が可能です。
成年後見制度の費用はどのくらいかかるのでしょうか?
- 法定後見
- 申し立て費用:1万円~5万円程度(専門家に依頼する場合は15~30万円程度)
- 後見人報酬:月額2~3万円(弁護士等が選任された場合)
- 任意後見
- 契約費用:公証役場での契約締結費用が約3万円、専門家に依頼する場合は15~30万円程度。
- 任意後見監督人の報酬:月額1~3万円程度。
法定後見は継続的な報酬が必要な場合が多いのに対し、任意後見は契約内容により柔軟に費用を調整できます。
任意後見と法定後見はそれぞれの特性に応じて活用できますが、どちらの制度を選ぶにしても、早期の準備が重要です。認知症発症後では選択肢が限られてしまうため、元気なうちに計画的に進めることが必要です。
以上を司法書士事務所の相続サイトのブログ用にまとめました。